マダニ
春から夏にかけては、マダニの活動が活発化します。
活動が盛んになるため、マダニに咬まれる危険性が高まります。
山林や草地などマダニが生息しているような場所に立ち入る際や農作業を行う際には、 マダニに咬まれないように以下を参考に対策をとってください。
マダニに咬まれないために
- 草むらや藪など、マダニが多く生息する場所に入る場合には
- 長袖・長ズボン(シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる、または登山用スパッツを着用する)
- 足を完全に覆う靴(サンダル等は避ける)、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻く等、肌の露出を少なくすることが大事です。
- 服は、明るい色のもの(マダニを目視で確認しやすい)がお薦めです。
- 靴や服の上から虫除けスプレーを使用すると効果があります。
- 家に入る前に上着や作業着などを脱ぎ、マダニなどを家に持ち込まないようにしましょう。
- 草むらから帰った後は、すぐに入浴し、体にマダニがついていないか確認しましょう。
マダニに咬まれたら
- マダニは、皮膚に口を突っ込んで吸血します。吸血中は痛みもないため、取り除こうと無理に引き抜くと先がちぎれて体内に残ります。
- 吸血中のマダニに気付いたときは、早めに医療機関で処置してもらってください。
- マダニに咬まれた後、数週間は体調の変化がないか注意し、発熱などの症状があった場合は、医療機関へ受診をお願いします。医療機関の受診の際には、マダニに咬まれたと担当医師へお伝えください。
マダニにご注意を(厚生労働省) (PDFファイル: 10.0MB)
マダニ等による感染症に注意しましょう!(大阪府ホームページ)
マダニが媒介する感染症
| 症状 | ||
|---|---|---|
| SFTS | 6日~2週間 | 発熱、消化器症状、全身倦怠感など |
| 日本紅斑熱 | 2~8日 | 発熱、頭痛、発疹、全身倦怠感など |
| ツツガムシ病 | 5日~14日 | 発熱、ダニの刺し口、発しんなど |
注意:重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、日本紅斑熱、つつがむし病等のダニ媒介感染症は、ウイルスや病原体を保有した動物を吸血したダニの体内でウイル スが増殖、そのダニがヒトを吸血することで感染します
マダニについて
野外にいる吸血性の大型のダニ(1~4ミリメートル)です。野山や公園の草むら、畑、あぜ道などにも生息しています。
春から秋(3月~11月)にかけて活動が活発になりますが、冬季も活動する種類もいます。
マダニの姿は大きく変化します
写真はタカサゴキララマダニです。

吸血前(1~4ミリメートル)

吸血後(体重は100倍以上に)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 管理・医療グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6400
メールフォームによるお問い合わせ
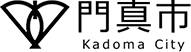




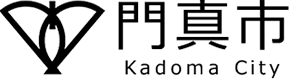


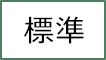
更新日:2024年05月24日