国民健康保険料の納付・計算
納付書または口座振替による納付(普通徴収)
納付回数は6月~翌年3月の年10回(1期~10期)です。
納期限は各月の末日です。(7期分は12月25日です)
ただし、各月末日が土曜日、日曜日および祝日の場合は、これらの日の翌日となります。
| 納付月 | 納期限 | |
|---|---|---|
| 令和7(2025)年4月 | 納付なし | |
| 令和7(2025)年5月 | 納付なし | |
| 令和7(2025)年6月 | 1期 | 令和7(2025)年6月30日 |
| 令和7(2025)年7月 | 2期 | 令和7(2025)年7月31日 |
| 令和7(2025)年8月 | 3期 | 令和7(2025)年9月1日 |
| 令和7(2025)年9月 | 4期 | 令和7(2025)年9月30日 |
| 令和7(2025)年10月 | 5期 | 令和7(2025)年10月31日 |
| 令和7(2025)年11月 | 6期 | 令和7(2025)年12月1日 |
| 令和7(2025)年12月 | 7期 | 令和7(2025)年12月25日 |
| 令和8(2026)年1月 | 8期 | 令和8(2026)年2月1日 |
| 令和8(2026)年2月 | 9期 | 令和8(2026)年3月1日 |
| 令和8(2026)年3月 | 10期 | 令和8(2026)年3月31日 |
4月~3月の12カ月分(1年間分)の保険料を10等分し、納付は6月から始まります。
注意:各1期分に相当する額は約1.2カ月分の保険料
4月から国民健康保険の資格がある場合

年度途中で国民健康保険に加入された場合
例1 7月中に健康保険の資格を喪失し、7月中に国民健康保険の加入手続きをした場合

注意:国民健康保険の加入申請をした月の翌月に国民健康保険料決定通知書をお送りします。
例2 10月中に健康保険の資格を喪失し、12月中に国民健康保険の加入手続をした場合

注意:国民健康保険は健康保険の資格を喪失した日まで遡って保険料を納付いただきます。
年度途中で国民健康保険を脱退された場合
例3 年度当初から国民健康保険加入者で、12月中に健康保険の資格を取得し、12月中に国民健康保険の脱退手続をした場合

注意1:新しい健康保険に加入した月以降の国民健康保険料の賦課がなくなります。
注意2:新しい健康保険に加入した場合は、必ず国民健康保険の脱退手続をしてください。
年金からの天引きによる納付(特別徴収)
次のすべてに当てはまる人は、4月~翌年2月の年金支払月の6回で、年金からの天引きにより納付してもらいます。
1.世帯主が国民健康保険の被保険者
2.世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳~74歳
3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上
4.世帯主の介護保険料が特別徴収されている
5.国民健康保険料と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えない
注意1:特別徴収(年金からの天引き)ではなく口座振替を希望する場合は、口座振替により納付することができます。口座振替を希望する場合は申請が必要となりますので、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)、口座振替の通帳を持参のうえ、健康保険課までお越しください。
特別徴収される月の3カ月前の月末までに手続きをすると、その月以降の特別徴収は中止され、口座振替により納付してもらうことになります。
(例)7月末までに手続きをすると、10月以降の特別徴収は中止され、10月から口座振替により納付してもらうことになります。
注意2:口座振替を希望しない場合、手続きは不要です。
注意3:年金から支払われた保険料は、その年金を受給した人に社会保険料控除が適用されますが、口座振替に変更した場合は、口座振替により支払った人に社会保険料控除が適用されます。そのため、世帯全体の所得税や住民税が変更となる場合がありますので、ご留意ください。
注意4:口座振替に変更した場合でも、保険料が未納となった場合は、特別徴収となることがあります。
国民健康保険料の計算
国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料、介護分保険料で構成され、それぞれは、前年中の所得に応じた「所得割」、被保険者の人数に応じた「均等割」、全世帯が負担する「平等割」の合計で計算します。
被保険者の中に40歳~64歳の人を含む世帯…(1)+(2)+(3)の合計額
被保険者の中に40歳~64歳の人を含まない世帯…(1)+(2)の合計額
(1)医療分保険料…すべての世帯が負担
(2)後期高齢者支援金分保険料…すべての世帯が負担
(3)介護分保険料…被保険者の中に40歳~64歳の人(介護第2号被保険者)がいる世帯にのみ負担
注意1:40歳の誕生月(1日が誕生日の人は前月)から介護分保険料が賦課されます。
注意2:65歳の誕生月(1日が誕生日の人は前々月)の前月まで介護分保険料が賦課されます。
医療分
- 所得割:被保険者の令和6(2024)年中の基準総所得金額(下記参照)×9.30パーセント
- 均等割:被保険者数×3万4424円
- 平等割:一世帯当たり3万3574円
1~3の合計額が世帯の年間医療分です
賦課限度額は65万円
後期高齢者支援金分
- 所得割:被保険者の令和6(2024)年中の基準総所得金額(下記参照)×3.02パーセント
- 均等割:被保険者数×1万1034円
- 平等割:一世帯当たり1万0761円
1~3の合計額が世帯の年間後期高齢者支援金分です
賦課限度額は24万円
介護分
- 所得割:被保険者の令和6(2024)年中の基準総所得金額(下記参照)×2.56パーセント
- 均等割:被保険者数×1万8784円
1、2の合計額が世帯の年間介護分です
賦課限度額は17万円
年度途中に40歳になる人は、40歳到達日(誕生日の前日)の属する月より介護分保険料の負担が必要になり、翌月以降(ただし、40歳到達日の属する月が4月の場合は、6月以降)の納期で按分した保険料を翌月から納付することになります。
また、年度途中に65歳になる人は、65歳到達日(誕生日の前日)の属する月の前月まで介護分保険料の負担が必要になり、翌年3月までの納期で按分した保険料を納付することになります。
注意:介護保険法施行規則などで規定されている特定の施設(介護保険適用除外施設)に入所している人は介護保険の適用から除外されますので介護分がかかりません。介護保険適用除外施設に入所する場合は健康保険課へ必ず届け出をしてください
例1 年度途中で40歳を迎えられる場合(対象者の方が10月誕生日の場合)

注意1:1日が誕生日の人はその前月から介護分を納付いただきます。
注意2:1日が誕生日の人は誕生日当月に介護分の保険料が賦課された通知書をお送りします。
例2 年度途中で65歳を迎えられた場合(対象者の方が10月誕生日の場合)

注意1:1日が誕生日の人はその前々月まで介護分を納付いただきます。
注意2:6月にお送りする通知書は上記の保険料で通知します。
75歳を迎えられると後期高齢者医療保険制度に移行します
後期高齢者医療保険制度は、高齢者の医療を国民全体で支え、高齢者が将来にわたり、安心して医療を受けられるようにするために、創設された制度です。
これまで国民健康保険や会社の健康保険などで医療給付を受けていた75歳を迎えられた人は、後期高齢者医療制度で医療給付を受けることとなります。
75歳を迎えられると、国民健康保険料の納付がなくなり、後期高齢者医療保険料の納付が始まります。
例1 年度途中で75歳を迎えられる単身世帯の場合(対象者の方が10月誕生日の場合)

注意1:5月から7月が誕生日の人は6月に国民健康保険料を加入月分納付いただきます。(4月が誕生日の人は国民健康保険料の通知はありません。)
注意2:8月以降に75歳を迎えられる人は誕生日の前月までの期別割額を納付いただきます。
注意3:6月にお送りする通知書は上記の保険料で通知します。
例2 年度途中で75歳を迎えられる場合で複数世帯の場合(対象者の方が10月誕生日の場合)

注意1:6月にお送りする通知書は上記の国民健康保険料で通知します。
(国民健康保険料と後期高齢者医療保険料を重複して納付することはございません。)
「基準総所得金額」とは
所得割の計算には、年金・給与・事業所得などと、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得などの所得を用います。基準総所得金額とは、世帯員各々の「前年中の総所得金額等から43万円を差し引いた金額」を合計した額です。
- 年金所得…公的年金等収入金額-公的年金等控除 注意:非課税年金(遺族年金・障害年金)は年金所得に含みません
- 給与所得…給与収入金額-給与所得控除
- 事業所得…事業収入金額-必要経費
- 土地等譲渡所得…譲渡所得金額-特別控除 注意:退職所得は「総所得金額等」に含みません
保険料の期割額の計算方法(門真市国民健康保険条例第16条第3項より)
- 国民健康保険料(年間)を10で割る
- 10で割った額に1円未満の端数があるときは1期に合算
計算例
例1
加入者(世帯主Aさん・41歳):令和6(2024)年中所得・事業所得200万円
注意:基準総所得金額=Aさん:200万円-43万円(基礎控除額)=157万円
医療分
所得割=157万円×9.30パーセント=14万6010円
均等割=3万4424円×1人=3万4424円
平等割=1世帯当たり3万3574円
合計21万4008円
注意:1円未満は切り捨て
後期高齢者支援金分
所得割=157万円×3.02パーセント=4万7414円
均等割=1万1034円×1人=1万1034円
平等割=1世帯当たり1万0761円
合計6万9209円
注意:1円未満は切り捨て
介護分
所得割=157万円×2.56パーセント=4万1448円
均等割=1万8784円×1人=1万8784円
合計 5万9932円
注意:1円未満は切り捨て
国民健康保険料(年間)
21万4008円(医療分)+6万9209円(支援金分)+5万9932円(介護分)=34万3149円
保険料の期別割額
1期(6月):3万4323円
2期(7月):3万4314円
3期(8月):3万4314円
4期(9月):3万4314円
5期(10月):3万4314円
6期(11月):3万4314円
7期(12月):3万4314円
8期(1月):3万4314円
9期(2月):3万4314円
10期(3月):3万4314円
合計:34万3149円
例2
加入者(世帯主Bさん・58歳):令和6(2024)年中給与収入400万円
加入者(妻Cさん・56歳):令和6(2024)年中給与収入103万円
所得(給与収入から給与控除額を差し引いて給与所得を算出)
Bさんの場合:400万円-124万円(給与控除)=276万円
Cさんの場合:103万円-55万円(給与控除)=48万円
基準総所得金額(給与所得から基礎控除額を差し引いて基準総所得金額を算出)
Bさんの場合:276万円-43万円(基礎控除額)=233万円
Cさんの場合:48万円-43万円(基礎控除額)=5万円
世帯の基準総所得金額=233万円+5万円=238万円
医療分
所得割=238万円×9.30パーセント=22万1340円
均等割=3万4424円×2人=6万8848円
平等割=1世帯当たり3万3574円
合計32万3762円
注意:1円未満は切り捨て
後期高齢者支援金分
所得割=238万円×3.02パーセント=7万1876円
均等割=1万1034円×2人=2万2068円
平等割=1世帯当たり1万0761円
合計10万4705円
注意:1円未満は切り捨て
介護分
所得割=238万円×2.56パーセント=6万0928円
均等割=1万8784円×2人=3万7568円
合計9万8496円
注意:1円未満は切り捨て
国民健康保険料
32万3762円(医療分)+10万4705円(支援金分)+9万8496円(介護分)=52万6963円
保険料の期別割額
1期(6月):5万2699円
2期(7月):5万2696円
3期(8月):5万2696円
4期(9月):5万2696円
5期(10月):5万2696円
6期(11月):5万2696円
7期(12月):5万2696円
8期(1月):5万2696円
9期(2月):5万2696円
10期(3月):5万2696円
合計:52万6963円
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ
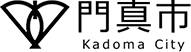




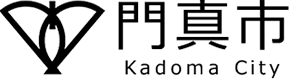


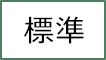
更新日:2025年06月05日