給与からの特別徴収に係る事務(事業所の方へ)
給与支払報告書の提出
所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、当該給与の支払いを受けている人に係る前年中の給与所得などを記載した給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を、当該給与の支払いを受けている人の賦課期日(1月1日)に居住している市区町村に提出する必要があります。
(根拠法令 地方税法第317条の6および第317条の7)
提出期限
毎年1月31日まで
対象
給与支払者は、「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、前年中に支払った給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員(パート、アルバイト、法人役人、弁護士、司法書士、税理士などを含む)の給与支払報告書を提出する必要があります。
注意:従業員が個人で確定申告をしている場合も提出が必要
注意:退職者の給与支払報告書は、退職日現在の住所地の市区町村に提出が義務付けられています。なお、「退職した年の給与支払額が30万円以下の場合は提出を省略することもできる」という規定がありますが、提出することで、納税者の申告忘れの減少にもつながります。支払金額にかかわらず、提出のご協力をお願いします
提出後に異動があった場合
給与支払報告書を提出した人のうち、4月1日現在、給与の支払いを受けなくなった人がいる場合は、4月15日までに、「市民税・府民税 給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。(根拠法令 地方税法第317条の6第2項)
市民税・府民税 給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 1.3MB)
提出方法
個人別明細書
在職者:1月1日現在の従業員などの住所地の市区町村に提出
退職者:退職時における従業員などの住所地の市区町村に提出 注意:平成29(2017)年度(平成28(2016)年分)からの給与支払報告書は、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、法人番号および個人番号の記載が必要。記載方法は、国税庁ホームページ参照
国税庁ホームページ(給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と手引)のホームページはこちら
総括表
個人別明細書を提出する場合は、まとめとして総括表を1枚添付のうえ提出してください。「報告人数」欄には、給与支払報告書を提出する人数を記載してください。特別徴収(住民税を給与から天引き)の場合は「在職者」の欄に、普通徴収(住民税を個人で納付)の場合は「退職者等(退職者・乙欄等)」の欄に人数を記載してください。普通徴収(従業員自身で納付)の該当者がいる場合は、下記の「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を給与支払報告書提出時に添付してもらうことになります。また、報告人数の計に記載された人数と、個人別明細書の提出件数は必ず一致させてください。
普通徴収切替理由書(兼仕切紙)注意:特別徴収のみの場合は不要
指定番号、事業所名、普通徴収対象者の人数を理由別に枠の中に記載し、普通徴収対象者(特別徴収できない人)の給与支払報告書個人別明細書の上に付けて提出してください。
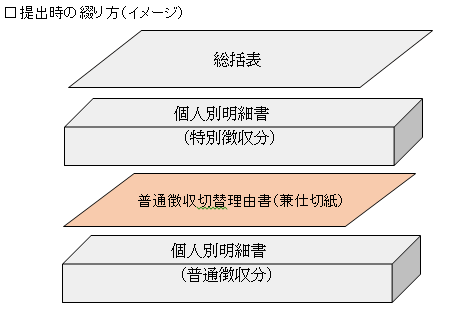
普通徴収として取り扱う給与受給者の人数と切替理由ごとの内訳と略号(a~d)は下記のとおりです。
(a)退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
(b)給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない人
(c)給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
(d)ほかから支給される給与から個人住民税が特別徴収されている人(乙欄適用者)
留意点
- エルタックスを利用する場合は、切替理由a~dのいずれかを摘要欄の最初に入力するとともに、普通徴収欄にチェックを入力してください。この場合、この切替理由書の提出は不要です
記載方法 - 総括表の普通徴収欄の人数と普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の合計人数が一致することを必ずご確認ください
- a~dの4項目以外が理由の場合、普通徴収は認められません
- 上記切替理由と同一の項目が記入されていれば、任意の様式での提出でも構いません
- 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の添付がない場合は、全従業員が特別徴収の対象となります
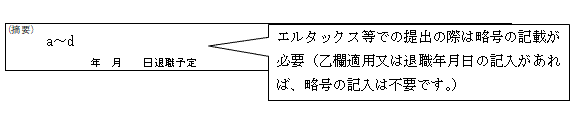
普通徴収切替理由書(兼仕切紙) (PDFファイル: 195.7KB)
郵送による提出
送付先
〒571-8585
「門真市役所」 課税課市民税グループ
注意:封筒に「給与支払報告書在中」と朱書きしてください
電子申告(eLTAX)による提出
eLTAXは、地方共同法人 地方税共同機構が運営するサービスです。従来、紙で行っていた市税に関する申告・届出がインターネットで行えます。
なお、給与または公的年金等支払報告書に記載する年分(例:平成31(2019)年1月の提出分であれば平成30(2018)年分)の前々年に税務署に提出した源泉徴収票の提出枚数が1000枚を超えていた場合、給与支払者は、市区町村に提出する給与支払報告書について、eLTAXまたは光ディスクなどでの提出が義務付けられています。
さらに、平成30(2018)年度の税制改正により、令和3(2021)年1月以降提出すべき給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスクでの提出基準が「1000枚以上」から「100枚以上」になりました。(例:平成31(2019)年1月の提出分が100枚以上の場合、令和3(2021)年1月はeLTAXまたは光ディスクでの提出が必要です。)
eLTAXのメリット
- チェック機能により入力や計算誤りを防ぐことが可能
- 一度の送信で複数の提出先に提出が可能
- 郵送料がかからない
eLTAXの利用方法および給与支払報告書の提出方法などは、地方税ポータルシステム エルタックス(eLTAX)のホームページをご覧ください。
地方税ポータルシステム エルタックス(eLTAX)のホームページはこちら
注意:普通徴収の該当者がいる場合は、個人別明細書の摘要欄に切替理由の略号(前述の普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を参照)を入力し、普通徴収欄にチェックを入力してください。
これらの入力がない場合は、全従業員が特別徴収の対象となります光ディスクなどによる提出
令和5(2023)年度の税制改正により、承認申請書の提出が不要になりました。他市区町村で提出の実績がなく、初めて光ディスク等で提出を行う場合はテストデータを作成し提出してください。詳細は「光ディスクなどで提出する際のデータの規格など」をご確認ください。
事前に必要な提出書類など
・テストデータ
注意:他市区町村ですでに承認されている場合、テストデータの提出は不要
注意:門真市では、光ディスクなどにより提出された場合でも、特別徴収税額決定通知書は紙のみで通知
注意:提出された光ディスクなどは返却不可
光ディスクなどで提出する際のデータの規格など
給与支払報告書を磁気テープまたは光ディスクなどで提出する際のデータ規格などは、下記を参照してください。(門真市ではCD-RとDVD-Rを推奨)
令和3(2021)年の所得に係る分を提出する場合
別紙2(給報磁気テープレコード内容及び記載要領) (PDFファイル: 290.5KB)
別紙4(給報光ディスク・磁気ディスクデータレコード及び記載要領) (PDFファイル: 204.0KB)
令和4(2022)年以降の所得に係る分を提出する場合
別紙1(給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合の光ディスク及び磁気ディスクの規格等) (PDFファイル: 166.1KB)
別紙4(公的年金等支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合の光ディスク及び磁気ディスクの規格等) (PDFファイル: 166.0KB)
(注意)令和4(2022)年以降、磁気テープによる提出は認められません。
令和5(2023)年以降の所得に係る分を提出する場合
別紙2(給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等) (PDFファイル: 157.4KB)
別紙4(公的年金等支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等) (PDFファイル: 125.5KB)
令和6(2024)年以降の所得に係る分を提出する場合
別紙2(給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等) (PDFファイル: 381.9KB)
別紙4(公的年金等支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等) (PDFファイル: 280.8KB)
令和7(2025)年以降の所得に係る分を提出する場合
別紙2(給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等) (PDFファイル: 310.2KB)
別紙4(公的年金等支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等) (PDFファイル: 227.4KB)
光ディスク及び磁気ディスクの規格等は「令和4(2022)年の所得に係る分を提出する場合」を参照してください。
給与所得に係る個人住民税の特別徴収
所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、従業員(短期雇用者、パート、アルバイト、役員などを含む)に支払う給与から個人住民税を差し引いて、各従業員が1月1日現在に居住している市区町村にそれぞれ納める義務が課されています。
(根拠法令 地方税法第321条の3および地方税法第321条の4)
平成30(2018)年度より個人住民税の特別徴収を徹底
大阪府と府内市区町村では、法令遵守と納税者の利便性向上の観点から、原則、すべての事業者(給与支払者)を、平成30(2018)年度から特別徴収義務者に指定し、特別徴収を徹底します。 注意:一部の自治体では、先行して平成28(2016)年度から段階的に取り組みを実施
注意:特別徴収が著しく困難であると認められるものは、特別徴収の方法によらないことができます。詳しくは上記「給与支払報告書の提出」参照 制度の詳しい内容などは、大阪府ホームページをご覧ください。
特別徴収の事務手引きのパンフレットはこちら (PDFファイル: 807.3KB)
給与所得に係る特別徴収税額の納入義務など
特別徴収の手続き
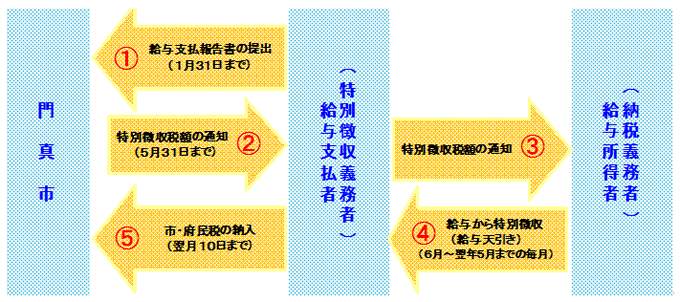
基本的な手続き
給与支払者は、従業員が1月1日に門真市に居住している場合、毎年1月31日までに門真市に給与支払報告書を提出します。
(2)特別徴収税額の決定通知書を送付(図2、3)毎年5月31日までに門真市から、特別徴収義務者として給与支払者に、特別徴収税額の決定通知書を送付します。年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から特別徴収を開始してもらいます。
また、特別徴収税額の通知書(納税義務者用)を送付しますので、各従業員にお渡しください。
(3)納入(図4、5)給与支払者は、給与から天引きした市・府民税を、翌月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌平日)までに門真市に納入します。
次のような事由が生じた場合は届出などが必要
納税義務者の退職などにより、特別徴収ができなくなった
未徴収税額を納税義務者本人が納める方法(普通徴収)に切り替える、または、退職の給与などから一括徴収するための届出が必要です。
納税義務者が転勤になり、転勤先で引き続き特別徴収することになった
転勤先などの新しい事業所で特別徴収を継続するための届出が必要です。 上記の場合、翌月の10日までに
「市民税・府民税 給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」
を提出してください。
市民税・府民税 給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 1.3MB)
異動者の特別徴収における留意点
退職などの場合における残りの特別徴収税額(月割額)
退職などで、給与から天引きできなくなる残りの月割額は、次のいずれかの方法により納めます。
- 納税義務者本人が、門真市から送付する納税通知書(納付書)により直接納める
- 給与支払者が、退職月の給与などから一括徴収して納める
どちらの方法をとるかは、退職などの時期により次の取扱方法となります。
| 退職などの時期 | 取扱方法 |
|---|---|
| 6月~12月 | ・本人の申出により、給与支払者が一括徴収可 ・一括徴収しない場合は、後日門真市から納税義務者本人へ送付する納税通知書により直接納付 |
| 1月~4月 | 本人の申出の有無に関わらず、給与支払者が一括徴収 |
転勤などにより、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合
特別徴収義務者は、納税義務者が転勤、転職した場合、
新しい勤務先へ徴収月や月割額を連絡
することになります。同時に、門真市に「市民税・府民税 特別徴収 給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出し、これに基づき門真市から新・旧それぞれの給与支払者へ「特別徴収税額の決定・変更通知書」を送付します。
新たに特別徴収することとなった
特別徴収へ切り替えるための「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。必ず、普通徴収で納めた額を納税義務者本人に確認のうえ、何月分から特別徴収することになるか、そのほか必要事項をご記入ください。これに基づき後日、門真市から給与支払者へ「特別徴収税額の決定・変更通知書」を送付します。
なお、普通徴収の納期限が過ぎたものは特別徴収の切替はできません。普通徴収の納期限が到来するまでに届出(依頼)書が届くようにご提出ください。
特別徴収を行う事業所の名称や所在地などが変更になった
特別徴収義務者の所在地や名称などの変更は届出が必要です。
給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所などは、「市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し承認を受けることにより、年2回に分けて納めることができます。
納期は、6月分~11月分は12月10日まで、12月分~5月分は6月10日(土曜日、日曜日、祝日のときは翌平日)までとなります。承認後の月割額が対象となりますので、それまでの月割額は通常の納入期限となります。
この特例は、退職手当などに係る特別徴収にも適用されます。
なお、承認を受けたのち、特例の要件に該当しなくなった場合または特例の取り消しをする場合は、すみやかに門真市へ届出をお願いします。
市民税・府民税 特別徴収税額の納期の特例に関する承認の申請書はこちら
市民税・府民税 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出書はこちら
市民税・府民税 特別徴収税額の納期の特例に関する取消届出書はこちら
下記からもダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ
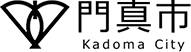




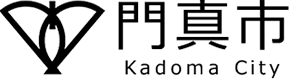


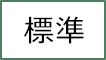
更新日:2025年12月09日