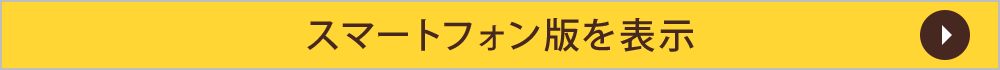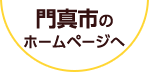保育の必要性の認定
幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、「教育・保育給付認定」または「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
なお、認定区分や認定内容に変更がある場合は、速やかに保育幼稚園課まで変更の申請をお願いします。
教育・保育給付認定
対象となる児童の年齢と保護者の状況により、区分が分かれ「保育の必要性」の認定審査後、「支給認定通知書」が交付されます。
| 認定区分 | 利用先 | |
|---|---|---|
| 1号認定 「教育標準時間認定」 |
満3歳以上の就学前子ども | 認定こども園(幼稚園部分)・新制度移行済幼稚園(注意) |
| 2号認定 「保育認定」 |
満3歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども | 認定こども園(保育所部分)・保育所・小規模保育事業 |
| 3号認定 「保育認定」 |
3歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども | 認定こども園(保育所部分)・保育所・小規模保育事業 |
注意:新制度移行済幼稚園(門真市内)は、すずらん幼稚園、さくら幼稚園、大阪ひがし幼稚園です。
注意:1号認定は、利用先を通じての申請となります
注意:「支給認定通知書」とは保育を必要とする資格を有することや、その区分、有効期限などを記載したものですので大切に保管してください。有効期限の到達時や記載内容に変更があった場合、返却の必要はありません。
また、必要に応じて「支給認定証」を発行することもできます。「支給認定証」は「支給認定通知書」と記載内容が同一のものですが、記載内容に変更があった場合、返却が必要となります。施設等に提出するなどの理由で「支給認定証」を必要とされる場合は保育幼稚園課にお申し出ください。
施設等利用給付認定
対象となる児童の年齢と保護者の状況により、区分が分かれ「保育の必要性」の認定審査後、「施設等利用給付認定通知書」が交付されます。
なお、認定を受けても利用する施設等の組み合わせや利用内容によっては、無償化とならない場合がありますのでご注意ください。
| 認定区分 | 利用先 | |
|---|---|---|
| 新1号認定 | 満3歳以上の就学前子ども | 新制度未移行幼稚園(注意) |
| 新2号認定 | 4月1日時点の年齢が3歳から5歳で、保育の必要性の認定を受けた子ども | 認定こども園(幼稚園部分)・幼稚園・認可外保育施設等 |
| 新3号認定 | 4月1日時点の年齢が3歳に満たない子どもで、保育の必要性の認定を受け、市町村民税が非課税世帯である子ども | 認定こども園(幼稚園部分)・幼稚園・認可外保育施設等 |
注意:新制度未移行幼稚園(門真市内)は、門真めぐみ幼稚園です。
注意:認定は、利用先を通じての申請となります。各利用施設が指定する日までに提出してください。
注意:申請前に施設等を利用している場合でも、認定開始日は申請日より前に遡及できませんのでご注意ください。
注意:「施設等利用給付認定通知書」とは有効期間内において国による幼児教育・保育の無償化の対象であることを証明するものですので、大切に保管してください。
注意:他市へ転出する人は、転出先の市町村での申請および認定が必要であり、申請書類も門真市の様式とは異なります。詳しくは転出先の市町村へお問い合わせください
保育の必要性の認定基準
|
|
状況 |
内容 |
|---|---|---|
|
1 |
就労 |
1月において、居宅外又は居宅内で子供と離れて64時間以上労働することを常態としている。 |
|
2 |
出産 |
妊娠中であるか、又は出産後、間がない。 |
|
3 |
疾病、負傷、障がい |
疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障がいがある。 |
|
4 |
親族の介護・看護 |
長期にわたり疾病の状態にあるか、又は精神もしくは身体に障がいがある親族を常時介護又は看護している。 |
|
5 |
災害復旧 |
震災、風水害、火災、その他災害の復旧に当たっている。 |
|
6 |
求職活動中 |
求職活動中(起業準備中含む)である。 |
|
7 |
就学中 |
学生、生徒である。 |
|
8 |
職業訓練中 |
職業訓練を受講している。 |
|
9 |
虐待 |
児童虐待を受けている、又は受けている恐れがある。 |
|
10 |
DV |
DV被害を受けている、又は受けている恐れがある。 |
|
11 |
育児休業(継続利用のみ) |
育児休業を取得する場合で、育児休業対象の子ども以外の子どもが引き続き保育所などを利用することが必要であると認められる。 |
|
12 |
その他 |
市長が認める前各号に類する状態にあること。 |
保育必要量(利用可能時間)
「保育認定」を行う場合、同時に保育必要量(利用可能時間)の認定も行います。 保育必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があります。
保育が必要な事由が「就労」の場合、就労時間が月120時間以上で「保育標準時間」となり、月120時間未満は「保育短時間」となります。その他の事由については、申請書類で審査のうえ必要量を決定します。
|
認定区分 |
保育の必要量(保育時間数) |
認定基準(例:就労時間) |
|---|---|---|
|
保育標準時間 |
保育が必要な範囲で、1日に最大11時間まで利用可能 |
月120時間以上 |
|
保育短時間 |
保育が必要な範囲で、1日最大8時間まで利用可能 |
月64時間以上120時間未満 |
注意:その他の事由については、申請書類で審査のうえ、必要量を決定させていただきます。
注意:「保育標準時間」認定となるお子さんは、「保育短時間」認定を希望することもできます。希望される場合は申請が必要です。
注意:開所時間などの設定は、施設等によって異なります。
お子さんをお預かりできる時間は、「保育が必要な時間」になります。例えば、就労を理由として施設等を利用されている方は、勤務時間と通勤時間を合わせた時間になります。買い物、食事や通院等、保育の必要性の事由と直接関係ない時間は含まれませんのでご注意ください。
保育を利用できる時間帯については、施設ごとに決まっています。
また、入園当初は、お子さんが施設等に慣れるまでの間、「慣らし保育」があるため、通常より保育時間が短くなることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 保育幼稚園課 保育幼稚園グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6757
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年10月01日