土地の評価方法
土地の評価のしくみ
土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目とは
土地の利用形態による区分のようなもので、固定資産評価基準では田や畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地の9種類に区分されています。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の土地の現況により地目を認定します。
土地の評価
土地の評価は、地目別に異なりますが、市内の一部の土地(調整区域内の農地や大工場など)を除いて路線価を用いて評価額を算定します。
土地の評価額算定の計算式(一例)
評価額=路線価×補正率×地積
路線価とは
市街地などにおいて道路につけられた価格のことで、具体的にはその道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいい、路線価は窓口で一般に公開しています。なお、固定資産税では地価公示価格の7割を目途に評価しています。
全国地価マップはこちら(財団法人資産評価システム研究センターホームページ)
補正率とは
例えば間口が狭い、土地の形が不整形、角地で利便性が高いなど、それぞれ土地の状況に応じて路線価を減価または増価させるために適用する率です。
地積とは
原則として登記簿に登記されている地積によります。
しかし、登記簿に登記されている地積が現況の地積よりも大きいと認められる場合においては、その土地の地積は、現況の地積によります。(ただし、地積更正登記ができない場合に限る。)
このような場合、現況地積課税申出書及び土地家屋調査士等の有資格者が作成した求積図や測量図等をご提出いただくことで、現況地積を評価に用いることとなります。
提出にあたっての留意事項
- 提出の際は、土地家屋調査士等の有資格者が作成した求積図や測量図等を添付してください。なお、測量図と現況が一致していないと判断できる場合においては認定できない可能性があります。
- この申出は登記簿上の地積を変更するものではありません。
- 申出日以降に到来する賦課期日(1月1日)に係る年度分からの適用となり、遡及適用はありません。
- 申出日以降に当該地において登記地積が変更する登記が行われた場合には、登記地積が採用されます。
手続きを希望される場合は、電話または窓口、ページ下部「メールフォームによるお問い合わせ」より、一度お問い合わせください。
土地評価額の計算例
例:路線価が10万円で、補正率が0.95の100平方メートルの土地の評価額は?
10万円(路線価)×0.95(補正率)×100(地積)=950万円
評価額は950万円土地の課税標準額のしくみ
課税標準額は原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、土地については法律上の特例措置などが適用されるため、市内のほとんどの土地は評価額と課税標準額が異なっています。
住宅用地の場合
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(住宅用地が200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)のことで、その課税標準額は、評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地のことで、その課税標準額は、評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の2つがあり、その敷地上の家屋の居住部分の割合により、住宅用地の範囲は異なります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に「住宅用地の率」を乗じて得た面積に相当する土地
注意:住宅用地の率については下記PDFの「居住部分の割合と住宅用地の率」のうち専用住宅は(イ)、併用住宅は(ロ)(ハ)を参照
固定資産税(・都市計画税)に係る住宅用地特例制度のご案内 (PDFファイル: 124.9KB)
例1:150平方メートルの土地に1戸の専用住宅(床面積100平方メートル)が建っている場合
すべて小規模住宅用地となります。
(150平方メートル>200平方メートル)
例2:300平方メートルの土地に1戸の専用住宅(床面積100平方メートルが建っている場合
200平方メートルまでは小規模住宅用地、100平方メートルは一般住宅用地となります。
(100平方メートル×10=1,000平方メートルまで)
例3:1,000平方メートルの土地にマンション(住宅戸数10戸で床面積1,000平方メートル)が建っている場合
すべて小規模住宅用地となります。
(200平方メートル×10=2,000平方メートルまで)
住宅の敷地の用に供されている土地とは
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設を予定している土地、あるいは住宅を建設中の土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該住宅に代えてこれらの住宅を建替え中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難指示などが行われた場合には、避難指示の解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。
住宅建替え中の土地に係る特例について
住宅建替え中の土地で、次の(1)から(5)の要件を満たすものについては、住宅用地として取り扱います。
(1) 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地として認定されていた土地であること。
(2)当該土地において、住宅の建替えが当該年度に係る賦課期日において着手されていて、かつ当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。(住宅の新築に関する建築確認申請書を建築主事または指定確認検査機関に提出し、当該年度に係る賦課期日において建築確認がおりていることが確認でき、当該年度に係る賦課期日後の3月末日までに基礎工事が着手されているものを含む。)
(3)住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
(4)当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること(注釈1)。
(5)当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、建替え後に初めて到来する賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること(注釈1)。
注釈1:原則として同一であることとは、建替え後の当該土地(住宅)の所有形態が、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地(住宅)の所有者の配偶者、直系血族(その配偶者を含む。)、または配偶者の直系血族の場合をいう。
商業地等の宅地の場合
商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地や農地以外の土地など)は、原則として評価額の10分の7(都市計画税も同じ)が課税標準額になります。
門真市の市街化区域農地の場合
原則として評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)が課税標準額となります。
税負担の調整措置のしくみ
土地の固定資産税の負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)は、地域や土地によりばらつきがあるため、課税の公平性の観点からばらつきを均衡化させる調整措置が法律上とられています。そのため、課税標準額は「土地の課税標準額のしくみ」で説明した計算結果と一致しないことがあります。
負担水準の求め方
商業地等(非住宅用地)
固定資産税…前年度課税標準額÷評価額 都市計画税…固定資産税と同じ
小規模住宅用地
固定資産税…前年度課税標準額÷(評価額×6分の1) 都市計画税…前年度課税標準額÷(評価額×3分の1)
一般住宅用地 市街化区域農地
固定資産税…前年度課税標準額÷(評価額×3分の1) 都市計画税…前年度課税標準額÷(評価額×3分の2) 注釈:住宅用地、市街化区域農地の評価額に特例率を乗じたもの(上の表のカッコ内の計算式)を以下では本則課税標準額と呼びます
課税標準額の求め方
商業地等の場合
負担水準 0.7を超える
課税標準額…評価額の70%まで引き下げ
税額への影響…前年より下がる
負担水準 0.6以上0.7以下
課税標準額…前年度課税標準額を据え置き
税額への影響…前年と同額
負担水準 0.6未満
課税標準額…引き上げ(注釈1または注釈3適用)
税額への影響…前年より上がる
住宅用地 市街化区域農地の場合
負担水準 1.0を超える
課税標準額…本則課税標準額まで引き下げ
税額への影響…前年より下がる
負担水準 1.0未満
課税標準額…引き上げ(注釈2または注釈4適用)
税額への影響…前年より上がる
注釈1:商業地等は、原則、前年度課税標準額+評価額×5%が課税標準額
注釈2:小規模住宅用地、一般住宅用地や市街化区域農地は前年度課税標準額+本則課税標準額×5%が課税標準額
注釈3:注釈1の計算結果が評価額の60%を超える場合は、評価額の60%が課税標準額。また、注釈1の計算結果が評価額の20%を下回る場合は、評価額の20%が課税標準額
注釈4:注釈2の計算結果と本則課税標準額のいずれか低い額を適用。また、注釈2の計算結果が本則課税標準額の20%を下回る場合は、本則課税標準額の20%が課税標準額
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
メールフォームによるお問い合わせ
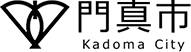




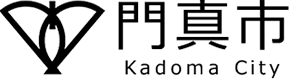


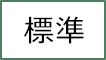
更新日:2025年12月23日