後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、高齢者の医療を国民全体で支え、高齢者が将来にわたり、安心して医療を受けられるようにするために創設された制度です。
これまで国民健康保険や会社の健康保険などで医療給付を受けていた75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度で医療給付を受けることとなります。
後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内のすべての市町村が加入する大阪府後期高齢者広域連合が行っています。門真市は申請や届出の受付、保険料の徴収などの窓口業務を行っています。
後期高齢者医療制度の被保険者となる人
75歳以上の人
75歳になる人は、それまで加入していた医療保険の種別に関わらず、75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。加入手続きは不要です。ただし、生活保護を受けている人は対象となりません。
65~74歳の人で、申請により広域連合が一定の障がいがあると認めた人(障がい認定)
65歳から74歳で一定の障がいがある人は、申請することで後期高齢者医療制度へ加入できます。認定日が加入日となります。
対象となる一定の障がいなどについてはこちら(大阪府後期高齢者医療広域連合)
障がい認定の申請
障がい認定の申請をする人は、次のものを健康保険課に持参してください。
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 障がい者手帳、療育手帳、障害年金1級~2級を受給している人は国民年金証書
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類(マイナンバーカードなど)
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状の様式はこちら(「後期高齢者医療の障害認定申請」にチェックを入れてください)
住所地特例
他の都道府県に転出したときは、原則、転出先の都道府県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。ただし、他の都道府県の住所地特定対象施設・病院等に転出した場合は、引き続き大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
マイナ保険証
医療機関・薬局を受診等する際は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードをご利用ください。
資格確認書の交付
新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合などの券面記載に変更があった場合は、資格確認書を交付します。病院などで医療を受けるときは窓口に提示してください。マイナ保険証を利用する人は資格確認書が不要です。
マイナ保険証有無にかかわらず資格確認書を7月下旬に送付
後期高齢者医療の新しい資格確認書(桃色)を令和7(2025)年7月3日に簡易書留で送りました。マイナ保険証の有無にかかわらず全ての被保険者に送りました。届いたときから使用できます。転送不可のため、住所地以外への送付を希望する場合は窓口または郵送で送付先変更を届け出てください。
令和8(2026)年7月31日までは、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を交付します。
新たに75歳になる人への送付
新たに75歳になる人には、誕生日の前月中旬に送ります。誕生日当日から使用できます。マイナ保険証を利用している人はそのまま利用できます。
送付先の変更
送付先の変更を希望する場合は、本人確認書類と送付先がわかるものを持って、健康保険課で申請してください。
- 送付先が個人宅の場合 送付先となる人の顔写真付き本人確認書類のコピー
- 送付先が施設等の場合 施設の名称と住所が記載されたパンフレット等のコピー
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピーを郵送してください。
資格確認書をなくしたとき
資格確認書をなくした人には資格確認書を再発行できます。本人確認書類を持って、健康保険課で申請してください。
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
郵送による申請も可能です。申請書を郵送してください。
資格確認書への限度区分の併記
新たに資格確認書へ限度区分の併記を希望する人は、健康保険課に本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)と資格確認書を持参または郵送で申請してください。
マイナ保険証を利用する人は、資格確認書への限度区分の併記が不要です。
- 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は廃止されました。
医療機関等窓口での自己負担割合
医療機関等窓口での自己負担割合は、一般の人は1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得者は3割となります。
自己負担割合についてはこちら(大阪府後期高齢者医療広域連合)
3割負担から2割または1割負担に変更できる場合(基準収入額適用申請)
前年中の収入額が次の要件に該当する人は、基準収入額適用申請をすることで、申請した月の翌月から2割または1割負担に変更されます。申請する人は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、収入額のわかる書類、資格確認書等を健康保険課に持参してください。
同一世帯に被保険者が1人の場合
被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
同一世帯に被保険者が複数いる場合
被保険者全員の収入額の合計が520万円未満のとき
同一世帯に被保険者が1人で、かつ、被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合
被保険者本人および70歳以上75歳未満の人の収入額の合計が520万円未満のとき
高額療養費の申請
後期高齢者医療制度では、高額療養費の受け取りについて事前申請は必要ありません。該当する人には、通常、診療月の約3か月後に大阪府後期高齢者医療広域連合から支給申請書が届きますので、振込先の口座情報などを記入のうえ健康保険課へ提出してください。
すでに口座情報を登録している人は支給申請が不要で、該当する人には、支給決定通知書が届きます。
高額療養費の振込先口座変更
高額療養費を振込先口座の変更を希望する場合は、本人確認書類と振込先となる口座が分かるもの(キャッシュカード・通帳など)を持って健康保険課で申請してください。
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
郵送による申請も可能です。申請書のみを郵送してください。
高額療養費口座変更申請書見本 (PDFファイル: 277.0KB)
入院時の食事代
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
入院時食事療養費についてはこちら(大阪府後期高齢者医療広域連合)
所得区分が低所得2の人で、過去12か月間の入院日数が90日を超える人は、食事療養標準負担額が1食あたり240円から190円になります。長期入院日数の届出をする人は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、過去12か月間で入院日数が90日(低所得2の認定を受けている期間)を超えていることが確認できる領収書・請求書等、資格確認書(持っている人のみ)を健康保険課に持参してください。
療養病床に入院したとき
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定)を除いた額を広域連合が負担します。
入院時生活療養費についてはこちら(大阪府後期高齢者医療広域連合)
特定疾病の療養を受けるとき
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部(第8.、第9.因子に由来するもの)、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、医療機関等の窓口で支払う自己負担限度額は月額1万円までとなります。ただし、医療機関と薬局の窓口では通常どおり支払います。
適用を受けるためには特定疾病療養受療証が必要です。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、更生医療券などの特定疾病であることがわかるもの、後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用していた特定疾病療養受療証(持っている人のみ)を健康保険課に持参して申請してください。資格確認書を持っている人は、資格確認書へ特定疾病区分を併記することもできます。
交通事故等にあったとき(第三者行為の届出)
交通事故や傷害事件など第三者の行為によって傷病について、後期高齢者医療制度で診療を受ける場合は、第三者行為による傷病届を提出してください。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、印鑑、交通事故の場合は交通事故証明書を健康保険課に持参してください。
療養費の支給申請
次の場合で、診療に要した費用の全額を自己負担したときは、申請により支給決定されれば、後日、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。ただし、医療費などを支払った日(全額を払い終わった日)の翌日から2年を過ぎると支給対象にはなりません。
- 急病などでやむを得ず、被保険者資格を確認できるものを提示せず診療を受けたとき
- 打撲・捻挫などで、柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けたとき
- 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入したときや輸血の生血代など
- 海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類を郵送してください。
療養費の申請に必要なもの
共通して必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)、領収書、申請者の口座情報がわかるもの
- 申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入しない場合は印鑑が必要
1~5の申請にそれぞれ必要なもの
1の場合 診療報酬明細書または診療内容明細書
2の場合 明細書等
3の場合 明細書等、医師の同意書
4の場合 明細書等、医師の意見書・治療用装具製作指示装着証明書等(靴型装具の申請時には装着する装具の写真の添付が必要)
5の場合 診療内容明細書(和訳の添付)、調査に関わる同意書、領収明細書(和訳の添付)、渡航履歴が確認できる書類(パスポート等)
給付内容(療養費・葬祭費など)についてはこちら(大阪府後期高齢者医療広域連合)
葬祭費の支給申請
亡くなられた被保険者の葬祭を行った人に5万円を支給します。ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりません。
葬祭費の申請に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 申請者の口座情報がわかるもの(預金通帳など)
- 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(申請者の氏名が宛名として記載された領収書・会葬礼状・請求書・葬祭執行証明書のいずれか)
- 死亡届、死亡診断書の写し(門真市役所以外で死亡届をした人)
- 申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入しない場合は印鑑が必要
代理人による申請も可能です。代理人が葬祭執行者と別世帯の人の場合、委任状が必要です。
郵送による申請も可能です。申請書と必要書類のコピーを郵送してください。
健康診査・歯科健康診査・人間ドック
大阪府後期高齢者医療広域連合は、健康診査・歯科健康診査を実施しています。
健康診査では糖尿病や高血圧症等の生活習慣病に加え、加齢に伴う心身の衰え等のチェックもできます。現在、生活習慣病で通院している人も積極的に受診しましょう。
歯科健康診査は歯だけでなく、加齢に伴う口の機能低下を含めてチェックをします。入れ歯を使用中の人も1年に1回歯科健診を受けましょう。
どちらも年度中に1回、無料で受診することができます。
人間ドックを受診した人は、健康診査を受診する必要はありません。
健診項目や実施登録医療機関など詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
健康診査の受診券をなくした場合
健康診査の受診券をなくした場合は再発行できます。健康保険課に電話するか窓口にお越しください。歯科健康診査の受診券はありません。
人間ドックの費用助成
人間ドックの受診に係る費用の一部を助成します。対象や条件など詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
人間ドックを受診し、いったん費用全額を自己負担した後、次の書類を健康保険課窓口へ持参して申請してください。
- 人間ドックの受診日が記載された領収書(コピー可)
- 検査結果通知書一式(コピー可)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 口座情報のわかるもの
申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者が自分で記入しない場合は印かんが必要です。検査結果通知書の写しの提出に応じられない場合は窓口にお伝えください。
関連ページ
後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?(政府広報オンライン)
後期高齢者制度に関する問い合わせ先
| 資格確認書、保険料等 | 資格管理課 | 電話06-4790-2028 |
| 高額療養費、健康診査、医療費通知等 | 給付課 | 電話06-4790-2031 |
| 予算、広報、議会等 | 総務企画課 | 電話06-4790-2029 |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ
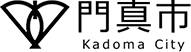




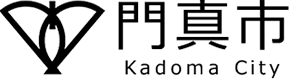


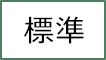
更新日:2026年01月22日