学生であって保険料を納付することが困難なとき(学生納付特例制度)
学生本人の前年所得が一定額以下であれば、保険料の納付が猶予されます。猶予された期間は、年金を受給するために必要な受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。
注意:学生納付特例対象の人は一般の免除制度を利用できません。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
対象
- 大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在籍している人
- 各種学校で1年以上の課程に在籍している人(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます)
- 国内に所在する海外大学(分校)で個別に指定されている課程に在籍している人
注意:対象となる学校は日本年金機構のホームページをご覧ください。
前年度に学生納付特例が承認されていた場合
申請は毎年必要ですが、前年度に学生納付特例が承認されていた人には、3月末から4月上旬に日本年金機構から更新用のハガキが送付されますので、必要事項を記入の上、返送することで申請ができます。ただし、前年度の申請時期によっては、ハガキが届かない場合がありますので、その場合は再度申請が必要です。
学生納付特例期間の取り扱い
- 学生納付特例の審査は申請年度の4月から翌年3月の期間で行います。
- 学生納付特例が承認された期間は老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
手続きに必要な物
- 本人確認のできる物
- 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
- 当該年度有効の学生証または在学証明書
注意:代理人が申請をする場合は、上記の書類に加えて代理人の本人確認ができる書類や委任状が必要となりますので以下のページをご確認ください。
代理人による国民年金の各種手続きは委任者本人自筆の委任状が必要になります
注意:申請年度または申請年度の前年において失業などの特別な事情がある場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、退職辞令などのうちのいずれか(コピーでも可)が必要な可能性があります。
申請書ダウンロード
申請に必要な書類(複写式の物)は、守口年金事務所または門真市役所市民課国民年金グループの窓口に設置しています。下記より申請書をダウンロードし、郵送で手続きをすることも可能です。
国民年金保険料 学生納付特例申請書 (PDFファイル: 1.6MB)
セルフチェックシート (国民年金保険料 学生納付特例申請用) (PDFファイル: 168.8KB)
免除手続き後の流れ・注意事項
- 審査の結果は、後日、日本年金機構からハガキが郵送されます。審査結果が届くまでには概ね2~3カ月かかります。
- 免除申請用紙を提出された場合でも、行き違いで納付書が届く場合があります。
- 免除申請は2年1カ月前までさかのぼることができますが、申請が遅れると申請前に生じた不慮の事故や障がいなどについて、障害基礎年金や遺族給付などを受給することができない場合がありますのでご注意ください。
- 前年の所得がある人が学生納付特例の申請をした場合、審査に必要な前年の所得の確定が6月頃となるため、審査結果が出るまでに通常よりも時間がかかることがあります。
追納制度
学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、老齢基礎年金の受給額が全額納付した場合と比較して少なくなります。
そこで、学生納付特例を受けた期間については、10年前までさかのぼって保険料を納めることができる「追納制度」が設けられています。
また、追納制度を利用して納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。
追納制度を利用される場合は守口年金事務所(電話:06‐6992‐3031)でのお申し込みが必要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
メールフォームによるお問い合わせ
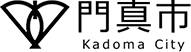




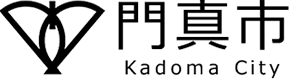


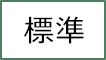
更新日:2024年04月01日