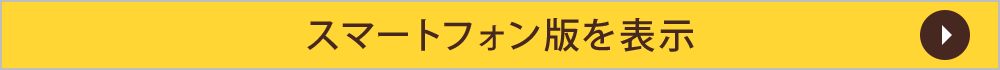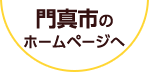予防接種
生後2か月から徐々に、お母さんからもらった免疫が減っていくときに、赤ちゃんがかかりやすい感染症から赤ちゃんを守るために、予防接種はとても大切です。予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。
予防接種を接種すると、病気に対する免疫をつけたり、重い症状になることを防げる場合があります。また、病気がまん延してしまうのを防ぐ効果もあります。
予防接種には「定期予防接種」と「任意予防接種(おたふくかぜやインフルエンザなど)」があります。
| 種類 | 対象年齢 | 回数 | 間隔 | |
|---|---|---|---|---|
| ロタウイルス | ロタリックス:生後6週から24週0日後までの間 | 2回 |
27日以上の間隔をおく どちらのワクチンも、生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間に接種完了するのが望ましい。 |
|
| ロタテック:生後6週から32週0日後までの間 | 3回 | |||
| BCG |
1歳になる前日まで 注意:両腕にステロイド剤を塗布している場合は接種できません |
1回 |
望ましい接種月齢:5か月から8か月まで |
|
|
小児用肺炎球菌 |
接種開始時に 2か月~7か月になる前日まで |
初回 3回 (注意3) |
初回:27日以上の間隔をおく | |
| 追加 1回 |
追加:1歳以降で初回接種終了後、60日以上の間隔をおく 標準的には1歳から1歳3ヶ月の間に接種 |
|||
| 接種開始時に 7か月~1歳になる前日まで |
初回 2回 (注意4) |
初回:27日以上の間隔をおく | ||
| 追加 1回 |
追加:1歳以降で、初回接種終了後60日以上の間隔をおく | |||
| 接種開始時に1歳~2歳になる前日まで | 2回 | 標準的には60日以上の間隔をおく | ||
| 接種開始時に2歳~5歳になる前日まで | 1回 | |||
|
(注意3)初回は標準的には1歳になる前日まで、ただし2・3回目は2歳になる前日までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。初回2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目の接種は行わない(追加接種は可能) (注意4)標準的には1歳になる前日まで |
||||
| B型肝炎 | 生後1歳の誕生日の前日まで | 3回 | 27日以上の間隔をおいて2回接種 さらに、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を接種 |
|
| 注意:出生直後に健康保険によりB型肝炎ワクチンの投与を受けたものについては定期接種の対象となりません。(残りの接種回数も保険適用となります。) | ||||
|
五種混合(DPT-IPV+Hib) ジフテリア |
2カ月から7歳6カ月になる前日まで
注意:すでに四種混合ワクチン、ヒブワクチンを接種している場合は、原則同一ワクチンで接種を完了させることになりますので、接種完了まで引き続き四種混合ワクチン、ヒブワクチンを使用します。 |
初回 3回 |
20日以上の間隔をおいて3回接種 注意:標準的には、生後2か月から生後7か月の間に接種を開始し、27日から56日までの間隔をおいて3回接種 |
|
|
追加接種1回 |
初回接種完了後、6か月以上の間隔をおいて1回接種 注意:標準的には6か月から18か月までの間隔をおいて接種 |
|||
| 二種混合(DT) ジフテリア 破傷風 |
11歳~13歳になる前日まで | 1回 | - | |
| 麻しん風しん混合 (MR) |
1期:1歳~2歳になる前日まで | 1回 | - | |
| 2期:小学校就学1年前(4月1日)~就学前日(3月31日)までの間 |
1回 | - | ||
| 麻しん風しんの混合予防接種については、1期・2期の対象の人でどちらか一方に罹患していても、混合又は単抗原のどちらかの予防接種が接種できます。 | ||||
| 水痘 | 1歳~3歳になる前日まで | 2回 | 1回目:標準的に1歳~1歳3ヶ月になる前日まで | |
|
2回目:3ヶ月以上 標準的には6ヶ月~12ヶ月までの間隔をおく |
||||
| 日本脳炎 | 1期:6か月~7歳6か月になる前日まで | 初回 2回 |
初回:6日以上 標準的には28日までの間隔をおく |
|
| 追加 1回 |
追加:初回終了後6か月以上 標準的には概ね1年おく |
|||
| 2期:9歳~13歳になる前日まで | 1回 | - | ||
| 注意:平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方で、日本脳炎の接種を差し控えておられた方は20歳未満の間、未接種分を接種することができます。ただし、2期の接種は1期を終了した9歳以上の方が対象となります。 | ||||
| ヒトパピローマ ウイルス感染症 (子宮頸がん予防) ワクチン |
小学6年生~高校1年生の女子 |
2回または3回 | サーバリックス(2価) 2回目:初回接種から1ヵ月後に接種 3回目:初回接種から6ヵ月後に接種 (注意5) |
|
| ガーダシル(4価) 2回目:初回接種から2ヵ月後に接種 3回目:初回接種から6ヵ月後に接種 (注意6) |
||||
|
シルガード9(9価) (注意7) 【2回接種の場合】 2回目:初回接種から6か月後に接種 【3回接種の場合】 2回目:初回接種から2か月後に接種 3回目:初回接種から6か月後に接種 |
||||
|
(注意5)この間隔で接種することができない場合は、2回目接種は初回接種から1か月以上の間隔をおく、3回目接種は初回接種から、5か月以上かつ2回目の注射から2か月半以上の間隔をおく
(注意7)1回目の接種を15歳までに受ける場合は、2回または3回接種のいずれか選択します。1回目の接種を15歳になってから受ける場合は、3回接種とします。シルガード9について詳しくはこちら。 |
||||
取扱医療機関(予約制)
門真市、守口市、寝屋川市、大東市、四條畷市の取扱医療機関で接種できます。取扱医療機関へ直接予約をしてください。
定期接種取扱医療機関に直接電話予約の上、接種当日必ず「母子健康手帳」と本人確認書類(マイナンバーカードや医療証等)をお持ちください。
注意:「母子健康手帳(または接種歴がわかるもの)」「本人確認書類」を忘れた場合は接種できません。
上記以外の市町村で接種を受ける場合は、事前に、予防接種依頼書の発行申請が必要です。
門真市こどもの予防接種依頼申請書 (PDFファイル: 612.7KB)
予防接種を受けることができない人
- 明らかに発熱している人
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- 当該疾病にかかる予防接種の成分によって、アナフィラキシーショックを起こしたことが明らかな人
- 麻しん、風しん、おたふくかぜ、水痘などが治って1か月以上経過していない人
- 突発性発しん、手足口病などが治って2週間以上経過していない人
- BCGについては、外傷などによるケロイドが認められる人
- 妊娠または妊娠の可能性のある人
- その他、予防接種をすることが不適当な状態にある人
予防接種を受ける際の注意
- 「予防接種の手引き」をよく読んで、予防接種の必要性や副反応についてよく理解しましょう。(「予防接種の手引き」はこども家庭センター母子保健グループにあります)
- 接種前日は入浴し清潔な肌着を着用してください。
- 接種されるお子さんの健康状態をよく知っている保護者が同伴してください。
- 副腎皮質ホルモン剤(ステロイド剤)を服用している場合は主治医へご相談ください。またBCGについては接種部位(両腕)にステロイド剤を塗布している場合は、少なくとも接種前日からの塗布は控えてください。
- 3~6か月以内に輸血、ガンマグロブリンの投与を受けた場合は、主治医へご相談ください。
予防接種の間隔(十分注意しましょう)
BCG・麻しん風しん混合・おたふくかぜ・水痘(みずぼうそう)などの生ワクチン接種後は27日間、別の生ワクチンを接種できません。
同種の予防接種を続けて受ける場合は規定の間隔をご確認ください。
予防接種を受けた後の注意
- 接種後30分間は、接種会場で子どもさんの様子を観察するか、医師とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応はこの間に起こることがあります。
- 接種後生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 入浴はさしつかえありませんが、注射した部位をわざとこすることはやめましょう。
- 接種当日は、いつもどおりの生活をし激しい運動はさけましょう。
- 接種後、高熱、けいれんなど異常をきたした場合は、医師の診察を受け、こども家庭センター母子保健グループまでご連絡ください。
定期予防接種を受けられなかった方について
定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病(厚生労働省令で定める疾病)にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種の機会を逃した方へ一定の期間内であれば定期の予防接種として接種できるようになりました。
長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった場合の手続きはこちら
造血細胞移植後の定期予防接種再接種費用助成事業について (平成30(2018)年7月から開始)
骨髄移植手術等の理由により、接種を受けた予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方(20歳未満)に対して、再接種費用を助成します。再接種の前に手続きが必要です。助成を希望される場合はこども家庭センター母子保健グループまでお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども家庭センター 母子保健グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6500
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月12日