国民健康保険料の減免と軽減
前年度から所得が減少するなどして保険料の納付が難しい人は、保険料の減免などを受けられる場合があります。
減免に関する共通事項
- 減免の申請は毎年度必要です。受付開始日は毎年6月1日です。
- 申請期限は納期限である各月末日です(月末日が土曜日または休日にあたるときはこれらの日の翌日。12月は25日)。納期限を過ぎた場合、さかのぼって減額されることはありません。納付済みの保険料には減免が適用されません。
- 所得状況が把握できない人がいる世帯は減免や軽減が適用されません。収入がない場合なども、健康保険課で所得の簡易申告をしてください。1月1日時点で19歳未満の人は申告していなくても構いません。
- 減免は世帯主に適用されるため、世帯主が変わったときは再度申請する必要があります。
- 減免適用後に世帯構成が変わったときは減免額が変更されることがあります。
- 減免適用の可否や減免額は国民健康保険料変更決定通知書によりお知らせします。
所得の減少に対する保険料の減免(申請が必要)
退職や倒産、廃業、休業、営業不振等で、同じ世帯の国民健康保険加入者の所得総額が前年に比べて30%以上減少する世帯は、保険料の所得割額が減額されます。
前年中の所得がない人には適用されません
この減免は所得に応じて算定される所得割額が減額されるものです。前年中の所得がない人は所得割額が0円のためこれ以上減額することができないことから適用されません。
| 所得の減少率 | 所得割額の減額率 |
| 100% | 100% |
| 90%以上100%未満 | 90% |
| 80%以上90%未満 | 80% |
| 70%以上80%未満 | 70% |
| 60%以上70%未満 | 60% |
| 50%以上60%未満 | 50% |
| 40%以上50%未満 | 40% |
| 30%以上40%未満 | 30% |
申請方法
次の書類を健康保険課に持参してください。
- 減免申請書(所得減少)
- 事実を証明する書類(表1参照)
- 収入状況がわかる書類(表2参照)
- 申立書(事実発生日やいつから収入が減少等したかを説明するもの)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、運転免許証等)
- 代理申請ができます。世帯主と同じ世帯でない人は委任状を持参してください。
- 郵送申請ができます。郵送の場合、2、3、5はコピーを送付してください。
| 会社を退職した | 退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証のいずれか |
| 給与が減少した | 減少前と減少後の給与明細書 |
| 事業を廃業した | 廃業等届出書 |
| 給与収入のある人 | 直近3か月の給与明細書、源泉徴収票、給与支払証明書(会社で作成してもらう必要があります)のいずれか |
| 年金収入のある人 | 年金額改定通知書、年金振込通知書、年金定期便のいずれか |
| 事業収入のある人 | 売り上げと経費がわかる帳簿、収支内訳書、収入状況申告書(帳簿等がないときに自ら作成できます)のいずれか |
- 世帯の所得総額を確認する必要があるため、同じ世帯の国民健康保険加入者全員の収入状況がわかる書類が必要です。
旧被扶養者への保険料の減免(申請が必要)
旧被扶養者とは、社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したとき扶養されていた人も社会保険等の資格を失いますが、その結果、国民健康保険へ加入した65歳以上の人のことです。旧被扶養者は次のとおり保険料が減額されます。
| 対象 | 減免額 | 減免期間 |
| 所得割額 | 全額 | 資格取得日から当分の間 |
| 均等割額 | 2分の1 | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間 |
| 平等割額(旧被扶養者のみで構成される世帯のみ) |
- 低所得世帯への保険料の軽減で5割軽減、7割軽減が適用されている世帯には、均等割額、平等割額の減免は適用されません。2割軽減が適用されている世帯には、平等割額が2割軽減前の額の2分の1に減額されます。
申請方法
次の書類を健康保険課に持参してください。
- 減免申請書(旧被扶養者)
- 旧被扶養者異動連絡票(市外から転入した人のみ)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、運転免許証等)
- 代理申請ができます。世帯主と同じ世帯でない人は委任状を持参してください。
- 郵送申請ができます。郵送の場合、2、3はコピーを送付してください。
災害に対する保険料の減免(申請が必要)
震災、風水害、火災等で住宅に著しい被害を受けた人は、被災された月以降最大12か月の間、保険料の所得割額、均等割額、平等割額が減額されます。
| 損害の程度 | 減免率 |
| 全壊・全焼 | 100% |
| 大規模半壊 | |
| 半壊・半焼 | 70% |
| 火災による水損または床上浸水 | 50% |
判定基準はこちら(内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」)
申請方法
次の書類を健康保険課に持参してください。
- 減免申請書(災害)
- り災証明書
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、運転免許証等)
- 代理申請ができます。世帯主と同じ世帯でない人は委任状を持参してください。
- 郵送申請ができます。郵送の場合、2、3はコピーを送付してください。
拘禁等された者への保険料の減免(申請が必要)
被保険者が刑務所や警察の留置場、少年院等に拘禁、収容されている場合は、国民健康保険の給付を受けられない期間の均等割額、所得割額が免除されます。対象期間が1か月未満の場合は、免除が適用されないことがあります。
申請方法
次の書類を健康保険課に持参してください。
- 減免申請書(拘禁)
- 収容証明書(拘禁等されている施設に相談)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、運転免許証等)
- 代理申請ができます。世帯主と同じ世帯でない人は委任状を持参してください。
- 郵送申請ができます。郵送の場合、2、3はコピーを送付してください。
倒産・解雇などによる離職者への保険料の軽減(申請が必要)
倒産・解雇などの理由で離職した人は保険料が減額されます。減額されるためには申請が必要です。離職の翌日から翌年度末までに健康保険課に申請してください。前年度に申請済みの人は改めて申請する必要はありません。
対象
離職日時点で年齢が65歳未満の人で、雇用保険受給資格者証の解職理由欄に記載されている番号が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」の人
(雇用保険受給資格者証を交付されていない人、特例受給資格者証、高年齢受給資格者証の人は対象外)
軽減内容
離職の翌日から翌年度末までの間、所得のうち給与所得を100分の30として保険料を計算します。
申請方法
次の書類を健康保険課に持参してください。
- 国民健康保険料軽減届出書(非自発的失業者用)
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、運転免許証等)
- 代理申請ができます。世帯主と同じ世帯でない人は委任状を持参してください。
- 郵送申請ができます。郵送の場合、2、3はコピーを送付してください。
低所得世帯への保険料の軽減(申請は不要・所得の申告が必要)
前年中の所得が次の基準額以下の世帯は、保険料の均等割額と平等割額が減額されます。申請は不要ですが、所得状況が把握できない人がいる世帯は、実際の所得が基準額以下であっても軽減が適用されません。収入がない場合なども、健康保険課で所得の簡易申告をしてください。1月1日時点で19歳未満の人は申告していなくても構いません。
| 基準額 | 軽減割合 |
| 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 | 7割 |
| 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+被保険者数×29万5000円 | 5割 |
| 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+被保険者数×54万5000円 | 2割 |
- 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える人や、公的年金等に係る所得のある人(65歳未満の人は60万円を超える人、65歳以上の人は125万円を超える人)のことです。
- 被保険者には、擬制世帯主と特定同一世帯所属者を含みます。
- 擬制世帯主とは、国民健康保険に加入していないが納付義務者である世帯主のことです。
- 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も同じ世帯に所属している人のことです。ただし、納付義務者が変更された場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
- 1月1日時点で65歳以上の人の判定基準所得は、公的年金等所得から15万円を控除した額です。
- 事業専従者控除がある人の判定基準所得は、控除前の額です。
- 専従者給与がある人の所得は判定基準に含みません。
- 被保険者数は4月1日時点で国民健康保険の資格を有する人数です。4月2日以降に加入した世帯はその日の加入者数です。
- 年度途中に世帯人数が変わっても軽減の取り消しや再判定は行いません。ただし、世帯主が変わったときは軽減の再判定を行います。
所得の簡易申告
簡易申告書を提出することで軽減判定を受けることができます。健康保険課へ持参または郵送してください。
特定同一世帯所属者がいる世帯への保険料の軽減(申請は不要)
特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も同じ世帯に所属している人のことです。
特定同一世帯所属者と同じ世帯に属し、被保険者が1人である世帯は、保険料の医療分と支援分にかかる平等割額が最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額されます。
子育て世帯への保険料の軽減(申請は不要)
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4(2022)年度以降の保険料から未就学児の均等割額を5割減額しています。低所得世帯では、7割、5割、2割軽減後の均等割額に対して、さらに5割減額されます。
産前産後期間の保険料の軽減(申請が必要)
令和5(2023)年11月1日以降に出産した(する)人は、保険料が減額されます。
新型コロナの影響による保険料減免の終了
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免は、国からの財政支援が終了したことに伴い令和4(2022)年度相当分の保険料で終了しました。令和5(2023)年度相当分の保険料では減免されません。
低所得者への保険料減免の廃止
令和5(2023)年度まで市独自で行っていた低所得者への保険料の減免は、令和6(2024)年度から減免基準が大阪府で統一されたことに伴いなくなりました。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
メールフォームによるお問い合わせ
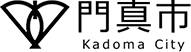




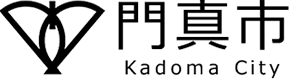


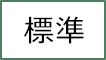
更新日:2024年04月17日